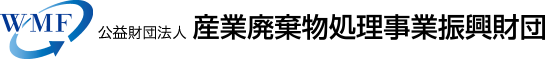資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律の一部施行について
はじめに
 環境省環境再生・資源循環局
環境省環境再生・資源循環局
廃棄物規制課課長補佐
山田 浩司
今般、資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律の一部の施行期日を定める政令(令和7年政令第2号。以下「施行期日令」という。)によって、基本方針、関係者の責務、廃棄物処分業者の判断の基準となるべき事項等に係る法の規定が令和7年2月1日から施行された。
また、これに伴い、資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律第十条第一項の要件を定める政令(令和7年政令第3号)、廃棄物処分業者の判断の基準となるべき事項について定める省令(令和7年環境省令第1号。以下「判断基準」という。)及び資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する施策を総合的かつ計画的に推進するための基本的な方針(令和7年環境省告示第2号。以下「基本方針」という。)が令和7年1月16日に公布され、同年2月1日から施行された。
1 法の趣旨
循環経済への移行は、持続可能な形で資源を効率的・循環的に有効利用することで、廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「廃棄物処理法」という。)第2条第1項に規定する廃棄物をいう。以下同じ。)の発生を抑制し、資源や製品の付加価値を生み出すことで、持続可能な形で新たな経済成長を目指すものである。また、循環経済への移行は、気候変動や生物多様性の保全、環境汚染の防止等の環境面の課題の解決に寄与するだけでなく、再生プラスチックなどの再生部品(廃棄物のうち有用なものであって、部品その他製品の一部として利用することができるもの又はその可能性のあるものをいう。以下同じ。)又は再生資源(廃棄物のうち有用なものであって、原材料として利用することができるもの又はその可能性のあるものをいう。以下同じ。)を積極的に活用した製品への市場ニーズの高まりへの対応という観点からは産業競争力の強化、レアメタルなどの資源の安定供給の確保という観点からは経済安全保障の基盤強化、地域の廃棄物を資源として活用することにより地域社会に付加価値をもたらすという観点からは地方創生・質の高い暮らしの実現につながるものである。
このように循環経済への移行は、環境面にとどまるものではなく様々な政策分野にかかわるものであり、こうした認識の下、第5次循環型社会形成推進基本計画(令和6年8月2日閣議決定)において、政府全体の方向性として、循環経済への移行を国家戦略としている。
世界各国で循環経済への移行が加速する中で、我が国においても循環経済への移行を加速していくには、物の製造、加工又は販売の事業を行う者(以下「製造事業者等」という。)が必要とする再生部品又は再生資源を長期的・安定的に供給できる体制を確保することが重要である。
また、地球規模の課題である気候変動問題の解決に向け、我が国においては、令和2年10月に、2050年までに温室効果ガスの排出を全体としてゼロにする「2050年カーボンニュートラル」を目標として掲げるとともに、その実現に向けて、あらゆる施策を総動員することとしている。
このうち、廃棄物分野については、我が国の温室効果ガス排出量全体の約3%を占めているものの、1990年代以降、温室効果ガス排出量は概ね横ばい推移しており、「2050年カーボンニュートラル」の達成のためには、資源循環・廃棄物処理業による脱炭素化を進めることが急務であるところ、そのためには、廃棄物分野の主な温室効果ガス排出源である焼却等される廃棄物の量を最小限とすることが重要である。
我が国の温室効果ガス排出量全体の約36%は、資源循環によって排出削減に貢献できる余地のある分野であるとの推計もあるところ、製造業等においても、資源循環を通じて原材料を代替することで温室効果ガスの削減効果が大きい分野があることから、再生部品又は再生資源を製品に活用して原材料の調達を最小限にしていくことが重要である。
このように、資源循環が重要になってきているところ、脱炭素社会の実現のためには、温室効果ガスの削減効果の高い資源循環を促進していくことが必要となる。
この点、資源循環に関する我が国の現状として、製造業等については、国際的な潮流として、投資の判断に当たって、原材料の調達から廃棄までのライフサイクル全体での温室効果ガス排出量の把握が問われることに加え、欧州では再生部品又は再生資源の利用に係る規制の策定が急ピッチで進められていることを受け、製造事業者等において、自らの事業に係る製品に関し、再生部品又は再生資源を原材料として活用する需要が高まってきており、再資源化(廃棄物の全部又は一部を部品又は原材料その他製品の一部として利用できる状態にすることをいう。以下同じ。)という資源循環の中核を担う廃棄物処理において、適正処理を前提としつつ、積極的に再生部品又は再生資源を生産することを促すことが重要である。
こうした状況を踏まえ、法は、脱炭素化と資源循環をこれまで以上に一体的に促進していくため、再資源化事業等の高度化(製造事業者等の需要に応じた再資源化事業(再資源化のための廃棄物の収集、運搬及び処分(再生を含む。以下同じ。)の事業をいう。以下同じ。)の実施その他の再資源化事業の効率的な実施のための措置、廃棄物から有用なものを分離するための技術の向上その他の再資源化の生産性の向上のための措置、再資源化の実施の工程を効率化するための設備の導入その他の当該工程から排出される温室効果ガス(地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)第2条第3項に規定する温室効果ガスをいう。以下同じ。)の量の削減のための措置、その他再資源化の実施に伴う温室効果ガスの排出(地球温暖化対策の推進に関する法律第2条第4項に規定する温室効果ガスの排出をいう。以下同じ。)の量の削減に資する措置を講ずることにより、再資源化の実施に伴う温室効果ガスの排出の量の削減の効果が増大することをいう。以下同じ。)を促進するための措置を講じたものである。
2 基本方針等(法第2章)
環境大臣は、資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する施策を総合的かつ計画的に推進するための基本的な方針を定めるものとすること(法第3条第1項)。
基本方針においては、適正処理による生活環境の保全及び公衆衛生の向上を前提とした上で、国民・消費者の協力を得つつ、産官学が連携しながら、循環型社会形成推進基本法(平成12年法律第110号)に規定する基本原則を踏まえ、質・量両面での資源循環の高度化を推進し、脱炭素化や自然再興、産業競争力強化、経済安全保障といった社会課題の解決、地方創生につなげることが重要であり、関係者の積極的取組により高度な資源循環を行い、その循環された資源を国内で活用することで、国内での資源確保につなげ、天然資源の消費が抑制され、環境への負荷が最小化された循環型社会を実現することなど、資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する基本的方向を定めるとともに(基本方針一)、再資源化事業等の高度化のための措置の実施に関して基本的事項を定めている(基本方針二)。
法に規定する関係者の責務及び当該責務を踏まえ基本方針において定める各主体の主な取組については下記の(1)から(5)のとおりである。
(1)国
地方公共団体、廃棄物処分業者(一般廃棄物処分業者(廃棄物処理法第7条第12項に規定する一般廃棄物処分業者をいう。)及び産業廃棄物処分業者(廃棄物処理法第14条第12項に規定する産業廃棄物処分業者をいう。以下同じ。)並びに事業者であって自らその産業廃棄物(廃棄物処理法第2条第4項に規定する産業廃棄物をいう。以下同じ。)の処分を行うものをいい、埋立処分又は海洋投入処分(廃棄物処理法第12条第5項に規定する海洋投入処分をいう。)を業として行う者を除く。以下同じ。)及び事業者に対し、それぞれの責務が十分に果たされるように必要な技術的援助を与えることに努めなければならないものとすること(法第4条第1項)。
地方公共団体、廃棄物処分業者、事業者、研究機関その他の関係者が相互に連携して製造事業者等の需要に応じた再生部品又は再生資源を廃棄物処分業者が供給する資源循環(以下「需要に応じた資源循環」という。)を促進するため必要な措置を講ずるよう努めなければならないものとすること(法第4条第2項)。
廃棄物処分業者の再資源化の実施の状況等の必要な情報を集約及び公表する情報基盤の整備、再生部品又は再生資源の利用拡大と安定供給、再生部品又は再生資源の品質に関する共通認識の醸成や研究開発の促進、関係者の取組が進むよう連携が実現している先進的事例や地域の優良な取組事例の収集・発信等に取り組むものとすること(基本方針一)。
高度再資源化事業の認定により、先進的な再資源化事業を支援するとともに、製造事業者等と廃棄物処分業者のマッチングやトレーサビリティ確保など、情報の共有による主体間の連携強化のために必要な取組の一層の具体化(基本方針二1)、高度分離・回収事業の認定による再資源化技術の向上の支援(基本方針二2)、再資源化工程の高度化の認定や、認定の事例集を作成し周知することによる廃棄物処理施設の脱炭素化の促進(基本方針二3)等に取り組むものとすること。
(2)地方公共団体
資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化を促進するよう必要な措置を講ずるよう努めなければならないものとすること(法第5条)。
引き続き廃棄物処理法に基づく廃棄物の着実な適正処理等に係る重要な役割を果たすとともに、資源循環を促進するよう地域における各主体間の連携・協働を促進するコーディネーター役として地域の循環資源や再生可能資源を活用した資源循環システムの構築等必要な措置を講ずるものとすること。また、市町村においては、地域住民の理解を得ながら一般廃棄物(廃棄物処理法第2条第2項に規定する一般廃棄物をいう。)の分別収集を進めることで再資源化が容易となる同じ性状・種類の廃棄物について、高度な再資源化が可能な廃棄物処分業者に委託するなどにより再資源化を進めるものとすること(基本方針一)。
(3)廃棄物処分業者
その再資源化事業等の高度化及び再資源化の実施に必要な措置を講ずるよう努めるとともに、再資源化の実施の状況の開示に努めなければならないものとすること(法第6条)。
循環資源の積極的な回収、再生部品又は再生資源の需要や再生部品又は再生資源利用率の把握、再資源化の実施状況の開示、再資源化事業等における温室効果ガス排出量の削減等に努めるものとすること(基本方針一)。
廃棄物から有用なものを適確に選別し、再資源化の実施の工程で得られる得られる再生部品又は再生資源の量を増加させるための取組の促進を図るものとすること(基本方針二2)。
破砕から成形までの再資源化の実施の工程の合理化、廃棄物処理施設への脱炭素化に資する設備の導入、再資源化の実施に当たっての廃棄物処理施設の運転状況の改善等に努めるものとすること(基本方針二3)。
(4)事業者
その事業活動に伴って生じた廃棄物を分別して排出するとともに、その再資源化を実施するよう努めなければならないものとすること(法第7条第1項)。
事業活動に伴って生じた廃棄物の分別・再資源化、製品が廃棄物となった場合における分離を容易にすること等の措置の実施、製品への再生部品又は再生資源の利用とその情報発信、需要に応じた資源循環の促進に努めるものとすること(基本方針一)。
廃棄物の処分を委託する際、性状等の情報提供など、得られる再生部品又は再生資源の量の増加に資するものとすること(基本方針二2)。
廃棄物の処分を委託するに当たり、製品のライフサイクル全体の脱炭素化の観点を踏まえ、再資源化の実施の工程の脱炭素化に資する廃棄物処分業者を選定することに努めるものとすること(基本方針二3)。
(5)国民・消費者
法において責務規定を設けていないが、資源循環を促進していくためにはその協力は不可欠であり、基本方針において、各主体の取組を踏まえ、地方公共団体の定めたルールに従って行う適切な分別排出や資源回収、リユース品や修理サービスの活用など 資源循環の取組について理解を深めるとともに、再生部品又は再生資源利用製品の選択など、生活者としての主体的な意識改革や行動変容に努めることとしている(基本方針一)。
さらに、基本方針は、地球温暖化対策の推進に関する法律第8条第1項に規定する地球温暖化対策計画及び循環型社会形成推進基本法第15条第1項に規定する循環型社会形成推進基本計画と整合性のとれたものであるものとし(法第3条第3項)、基本方針において、法に基づく認定制度の施行から3年の間に、国が高度な資源循環の取組に対して、100件以上の認定を行うなど、再生部品又は再生資源の質と量の確保等の資源循環の取組を一体的に促進するための措置を講じ、第5次循環型社会形成推進基本計画その他の施策と合わせて達成を目指していく、処分を行う廃棄物の数量に占める再資源化を実施すべき量の割合に関する目標等を定めている。
加えて、基本方針は資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する重要事項として、最終処分場の確保、地方公共団体との連携の促進、産官学の連携の促進、人材の育成、災害時対応、国際ルール作り等の国が取組を進めるべき事項についても定めている。
基本方針に基づいた各主体の取組による質・量両面での資源循環の高度化により、2050年ネット・ゼロや2030年ネイチャーポジティブの実現に貢献するとともに、再生部品又は再生資源の質・量の確保を通じ、再生部品又は再生資源の用途拡大・利用による新たな価値の創出につなげることで、産業競争力の強化やバリューチェーンの強靱化による経済安全保障の確保、地域の活性化や個性のある地域の創出への貢献が期待される。
3 廃棄物処分業者による資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化の促進(法第3章第1節)
(1)廃棄物処分業者の判断の基準となるべき事項
環境大臣は、資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化を促進するため、製造事業者等の再生部品又は再生資源に対する需要の把握並びに当該需要に応じた質及び量の再生部品又は再生資源の供給に関する事項、再資源化の生産性の向上のための技術の向上に関する事項、再資源化の実施の工程から排出される温室効果ガスの量を削減するための当該実施に用いられる廃棄物処理施設(一般廃棄物処理施設(廃棄物処理法第8条第1項に規定する一般廃棄物処理施設をいう。)又は産業廃棄物処理施設(廃棄物処理法第15条第1項に規定する産業廃棄物処理施設をいう。)をいう。以下同じ。)における設備の改良又はその運用の改善に関する事項、処分を行う廃棄物の数量に占める再資源化を実施する量の割合に関する目標の設定及び当該目標を達成するために計画的に取り組むべき措置に関する事項、その他再資源化事業等の高度化及び再資源化の実施の促進に関し必要な事項に関し、廃棄物処分業者の判断の基準となるべき事項を定めるものとすること(法第8条第1項)。
判断基準は、基本方針に即し、かつ、再資源化事業等の高度化及び再資源化の実施の状況、再資源化事業等の高度化に関する技術水準その他の事情を勘案して定めるものとすること(法第8条第2項)。
判断基準は、国が資源循環産業のあるべき姿への道筋を示し、再資源化に消極的であった廃棄物処分業者も含めて、産業全体の底上げを図るためのものであり、各廃棄物処分業者においては、それぞれの事項について可能な範囲での取組や段階的な実施を期待するものである。そのため、廃棄物処分業者において、再資源化の実施の状況が判断基準に規定する事項に照らして不十分な場合であっても、判断基準の施行後直ちに国による行政指導を実施するものではないが、各廃棄物処分業者においては、基本方針等を参考に、その処分を行う廃棄物の数量に占める再資源化を実施する量の割合に関する目標を設定するとともに、自らの再資源化の実施の状況を公表するなど積極的な取組の実施が期待される。国としても取組の実施に関する考え方をより具体的に示すため、廃棄物処分業者の所属する団体と連携して、説明会や研修を行うことなどについても検討していく。
判断基準で定める事項について主に期待される取組例等は下記の一から六のとおりである。
一 再生部品又は再生資源に対する需要の把握及び供給に関する事項(需要に応じた再生部品又は再生資源の規格及び量の把握)
・再生部品又は再生資源の性状に関する日本産業規格等の標準的な規格の参照
・地方公共団体や各種団体が運営する情報プラットフォームからの再生部品又は再生資源の需要及び供給先の情報収集
・自らの施設の処理能力から生産可能な再生部品又は再生資源の量の把握
二 技術の向上に関する事項(生産性を向上させる技術を有する設備の導入)
・再資源化の生産性を向上させる技術動向の把握
・再資源化の生産性を向上させる技術を有する設備の導入の検討
三 温室効果ガスの量を削減するための設備の改良又はその運用の改善に関する事項(省エネ型の設備への改良及び運転の効率化)
・再資源化の工程を効率化する設備の導入
・保有する設備の運用について、管理基準の設定(定期点検の実施、運転管理マニュアルの整備等)
四 再資源化の実施の目標の設定及び当該目標を達成するための措置に関する事項(目標設定及び目標達成に向けた計画的な取組)
・処分を行う廃棄物の数量に占める再資源化を実施する量の割合に関する目標の設定
五 その他再資源化事業等の高度化及び再資源化の実施の促進に関し必要な事項(人材育成・研修・労働環境の改善)
・各種団体が実施する、法令遵守、再資源化の高度化、労働安全衛生等に関する研修の従業員の受講
六 その他再資源化事業等の高度化及び再資源化の実施の促進に関し必要な事項(再資源化の実施の状況の公表)
・各社HPや環境省への再資源化の実施の状況の報告(任意報告を含む。)を通じた公表
再資源化の実施の状況に関し、国が取組を評価する際には、再資源化を前提としていない有害物質の処理が必要な廃棄物や個人情報の保護のための処理が必要な廃棄物など、再資源化が困難な一部の廃棄物についても勘案するものとする。
また、本通知においても定義しているとおり、「再資源化」とは「廃棄物の全部又は一部を部品又は原材料その他製品の一部として利用することができる状態にすること」を指す。そのため、例えば、中間処理産業廃棄物(廃棄物処理法第12条第5項に規定する中間処理産業廃棄物をいう。以下同じ。)の一部が製品等に利用することができる状態とされていれば「再資源化」に該当するものである。こうした場合において、再資源化の実施主体は、当該中間処理産業廃棄物を製品等に利用することができる状態にした産業廃棄物処分業者であり、当該中間処理産業廃棄物を生じた中間処理業者(廃棄物処理法第12条第5項に規定する中間処理業者をいう。以下同じ。)は再資源化の実施の主体と直接みなすことはできないが、我が国の産業廃棄物処理は各地域において複数の産業廃棄物処分業者の連携のもと実施される場合も多く見受けられることから、中間処理産業廃棄物を生ずる中間処理業者の再資源化の実施の状況に関し、国が取組を評価する際には、産業廃棄物処分業者間で連携した処理についても勘案するものとする。
循環型社会形成推進基本法においては、循環資源については、できる限り循環的な利用(再使用できるものは再使用、再使用されないものは再生利用、再生利用されないものは熱回収)が行われなければならないとされてており、まずは、循環的な利用を優先すべきものとした上で、「再資源化」はその範囲を広く捉えることが法の趣旨・目的に沿うものであり、脱炭素化に資する燃料の実用化が進められている昨今の状況を踏まえ、化石燃料を代替する燃料化についても法においては「再資源化」に該当するものとし、「製品」には燃料が含まれるものとする。一方で、廃棄物発電など直接熱回収を行う場合は「製品」にあたらないことから、法に基づく「再資源化」の定義には該当しないものと解される。
(2)特定産業廃棄物処分業者
環境大臣は、産業廃棄物処分業者であって、その処分を行った産業廃棄物の数量が政令で定める要件に該当するもの(以下「特定産業廃棄物処分業者」という。)の再資源化の実施の状況が、判断基準に照らして著しく不十分であると認めるときは、当該特定産業廃棄物処分業者に対し、その判断の根拠を示して、再資源化の実施に関し必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができるものとすること(法第10条第1項)。
また、環境大臣は、勧告を受けた特定産業廃棄物処分業者が、正当な理由がなくてその勧告に従わなかった場合において、再資源化の実施の促進を著しく阻害すると認めるときは、中央環境審議会の意見を聴いて、当該特定産業廃棄物処分業者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができるものとすること(法第10条第2項)。
我が国の産業廃棄物処分の現状を見ると、比較的規模の小さい産業廃棄物処分業者が多く存在しているが、当該産業廃棄物処分業者の処分量は全体の処分量としては多くないことを踏まえ、温室効果ガス排出量の削減を実効的に促進する観点から、国内全体の産業廃棄物処分量の総量に対し大多数の処分量の割合を占めている、当該年度の前年度において処分を行った産業廃棄物の数量が10,000トン以上の産業廃棄物処分業者、又は、当該年度の前年度において処分を行った廃プラスチック類の数量が1,500トン以上の産業廃棄物処分業者を「特定産業廃棄物処分業者」とするものである。
特定産業廃棄物処分業者への該当性は産業廃棄物処分業者ごとにより判断するものであり、国が勧告・命令を発出するに際しては各産業廃棄物処分業者が処分する廃棄物の種類、性状、事業環境等を勘案するものとする。例えば、3(1)において記載したとおり産業廃棄物処分業者間で連携した処理に加え、廃棄物の種類、性状、事業環境等に応じて再資源化の実施の状況は異なることから、処分を行う廃棄物の種類、性状、事業環境等についても勘案するものとする。
特定産業廃棄物処分業者に対する、国による監督等については特定産業廃棄物処分業者に係る規定にのみ及ぶものであり、廃棄物処理法に基づく権限によって実施される地方公共団体による監督等と重複又は不整合が生じるものではない。
なお、特定産業廃棄物処分業者は法の報告・公表制度の対象とされているが、報告・公表制度について規定している法第38条、第39条及び第40条は施行期日令によって施行される規定に含まれておらず、法の「公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行」するものとしており(法附則第1条柱書)、具体的な報告事項等については引き続き検討を進めていくものである。
4 その他
今般の法の一部規定の施行に当たり、基本方針等に即した取組が実施されることを期待するとともに、循環型社会の形成に向けた人材育成・相互連携等の促進や地域資源を活用した具体的な資源循環の取組の実施に向け、地方公共団体とも連携しつつ、脱炭素化と資源循環の取組を一体的に促進するための取組を進めてまいりたい。
そのほか、認定制度、登録調査機関、報告・公表制度等に係る法の規定については、法附則第1条柱書において、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものとしており、令和7年11月までに施行する必要がある。当該規定の施行に向けては、「中央環境審議会循環型社会部会静脈産業の脱炭素型資源循環システム構築に係る小委員会」や「再資源化事業等の高度化に関する認定基準検討 ワーキンググループ」での議論内容を参考に、環境省において検討を進めるとともに、関係者への意見聴取等を実施しているところであり、実効的な制度の実現に向けて引き続き積極的に御協力いただきたい。