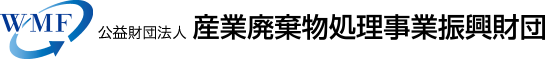特集(全国産業廃棄物担当者会議-議事3)
低濃度PCB廃棄物の適正処理
(公財)産業廃棄物処理事業振興財団 技術部長 川瀬 豊
PCBの基礎知識
PCBとはポリ塩化ビフェニル(Poly Chlorinated Biphenyl)の略称であり、ビフェニル分子に複数の塩素原子が結合した有機化合物の一群を指す。
PCBは、1881年にドイツで開発され、1929年に米国で量産化が開始され、それまでの鉱物油を原料とする工業油に比較して化学的に安定し、熱に強く、金属への攻撃性が低く、電気絶縁性が高い等の物性から、かつては広範に使用されていた。
一方、その化学的に極めて安定な物性故に、環境中で分解され難く長期間にわたって土壌、水、空気の中に存在し留まり、食物連鎖を通じて濃縮され易く、最終的には人間を含む高次の捕食者の健康に有害な影響を及ぼす。
人体への有害性としては、毒物や劇物に相当する強い急性毒性はないが、長期間の摂取により体内に蓄積し、目ヤニ増加やまぶたの膨張、爪や口腔粘膜の色素沈着や黒化、座瘡様の発疹(ニキビ)、肝臓の肥大や機能不全等の影響が確認されている。また国際がん研究機関(IARC)によって「人に対しておそらく発がん性がある」物質にも分類されている。
本邦においては、昭和43年(1968年)北九州市で発生した「カネミ油症事件(ライスオイルにPCBが混入し、それを摂取した多数の消費者が健康被害を受けた事件)」の原因物質としても知られている。
PCBの規制
これらPCBにおける有害性が明らかになると、1970年代後半から1980年代にかけて多くの国でPCBの製造と使用が規制された。国際条約においては1989年にバーゼル条約が採択されて越境移動と処分が規制され、2001年にストックホルム条約が締結されて残留性有機汚染物質(POPs)の使用と排出が制限された。
本邦においても、「PCBを含む機器や廃棄物の適切な管理と処理の促進」、「PCBによる環境汚染を防止し、国民の健康と安全を守る」、「PCBの処理に関する法的枠組みを整備し、関係者の責任の明確化」の三つを目的として事業者と自治体及び国の責務と役割を明確に規定する、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(以下、「PCB特措法」という。)が平成13年(2001年)7月に施行され、平成28年(2016年)8月には、同法の改正が行われた。
PCB特措法には、PCB廃棄物の識別、収集、運搬、処理、処理後の管理に関する詳細な規定が設けられている。
参考として、PCB特措法の大まかな内容を下記に条文抜粋の形で示す。
【保管等の届出(第8条)】
保管事業者は、毎年、都道府県と政令市に保管と処分の状況の届出を行う。
【期間内の処分(第10条)】
施行令において、定めた期限までの処分(低濃度PCB廃棄物の処分期限は令和9年3月31日)を規定する。
【譲り渡し・譲り受けの制限(第17条)】
PCB廃棄物は、原則、譲り渡し、譲り受けてはならない。
低濃度PCB廃棄物の定義
低濃度PCB廃棄物とは、PCB含有濃度が0.5(㎎/㎏)超から5,000 (㎎/㎏) 以下(*ただし可燃性PCB汚染物は10%以下)の廃棄物であり、トランスやコンデンサー等の電気機器類やその他の汚染物をいう。
適正処理のプロセス
低濃度PCB廃棄物の処理は、適正処理が法律で義務付けられており以下の①から④のようなプロセスが必要となる。
- 廃棄物の識別と分類
廃棄物が低濃度PCB廃棄物に該当するかどうかを識別して適切に分類することが求められ、必要があればPCB含有濃度の分析が必要となる。 - 低濃度PCB廃棄物の収集と運搬
低濃度PCB廃棄物は、安全に収集し運搬する必要がある。運搬中にPCBが漏洩しないように、密閉された容器を使用し、適切なラベルを貼付することが求められている。 - 低濃度PCB廃棄物の処理
低濃度PCB廃棄物は、環境大臣認定を取得した31カ所の無化処理認定施設と都道府県知事等の許可を取得した2カ所の無害化処理施設にて適正な処理が行われている。 - 処理後の管理
処理が完了した後も、処理結果を監視し、必要に応じて追加の対策を講じることが重要であるため、処理の過程や結果を詳細に記録し、保管することが求められている
持続可能な未来のために
低濃度PCB廃棄物の適正処理は、持続可能な未来を築くための重要なステップである。
適切な識別、収集、運搬、処理、処理後の管理を徹底することによってPCBの有害な影響を防ぎ、持続可能な社会の実現に貢献することができると考えている。
現代社会において、一人ひとりがこの問題に関心を持ち、積極的に取り組むことが求められる。私たち産業廃棄物処理事業振興財団も低濃度PCB廃棄物の適切な処理と管理を通じて、環境汚染を防ぎ、国民の健康と安全を守る役割の一助となることを目的に、皆様のご支援の下に日々活動しておりますので、今後も引き続きご指導のほどをよろしくお願いいたします。