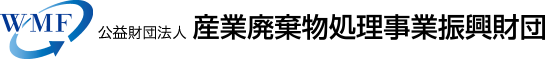第20期経営塾に参加して
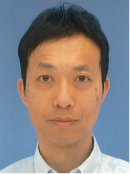 大青工業株式会社 佐藤貴彦
大青工業株式会社 佐藤貴彦
経営塾参加に至ったきっかけ
私は元来極度の人見知りである。それは幼少時代から父の仕事の関係で国内を転々とする生活を送っていたことに大きく関係していると思っている。新しい学校での登校初日はいつも緊張した。転校生だった自分はいつも同級生からの好奇の目にさらされた。私はその目がとても怖かった。無邪気な目線を送ってくる子もいれば、子供ながらに自分にとってどういう利益をもたらすかを見極めるかのような、そんな計算された目を向けてくる子もいた。転校生は初動が勝負、私は少しでも新しいクラスメートにうまく(無難に)溶け込むため、己を消すことにとにかく必死だった。目立てばいじめに遭うリスクがあったからだ。それは色々な転校生を見てきた中で学んだ自分なりの処世術だった。
そんな自分が今回経営塾に入塾するきっかけは今から二年ほど前に遡る。2022年末、運命のいたずらに導かれ、ひょんなことからこの産業廃棄物業界に入ることになった私は、縁もゆかりもない仙台でその人見知りを全開にしながら、右も左も分からないまま毎日を模索していた。当然だが周りに仕事のことや私生活のことを相談できる人間はいなかった。
そんな中、あの男が突然仙台の事務所に現れたのだ。
その男は初対面にも関わらず非常にフランクで、まるで自分の家でお茶を飲みながら談笑しているかのように、話したい事、聞きたいことをひたすら話しつづけ、そして嵐のように去っていった、「経営塾っていうのがあるんですよぉ、佐藤さんも来年の経営塾には是非参加してください~」という言葉を残して。幼少時代から常に相手の出方を伺いながら目立たないことを信条としてきた自分にとってこの男との出会いは衝撃的だった。そう、その男こそ産廃振興財団で経営塾の事務局をやっている男、兼子氏だった。
当然、警戒心全開中の私は翌年の経営塾には申込を忘れたふりをして参加しなかった。無事申込み期限をやり過ごし、やれやれこれでこの先1年も平穏な生活が送れる、と胸をなでおろした。
「天災は、忘れたころにやってくる」
その言葉通り、それからの一年後の2023年冬、経営塾のことを忘れかけていたころにまた兼子氏はやってきた。「入塾いただけると思ってお待ちしていたんですよ、なんで入ってくれなかったんですか!今年こそは是非お願いしますよ!」。
弊社社長からも、「経営塾の合宿、あれは楽しいぞ」というダメ押しの一言もあり、ついに私は観念した。
このように私の入塾の動機は決して積極的なものはなく、むしろ周りに外堀を埋められ逃げ場がなくなりやむを得ず、という超消極的なものであった。
だが、結果論になるが、この1年遅れの経営塾への入塾は今後の自分の人生においてかけがえのないものを残してくれたように思う。1年早くても1年遅くてもダメだったかもしれない。こんな自分を懲りずに何度もお誘いいただき貴重な機会を提供してくれた財団の兼子氏には感謝の言葉しかない。
いよいよスタートした経営塾
そんなこんなでかなり後ろ向きの動機で入塾した私であったが、とにもかくにも6月に開塾式がありいよいよ約半年に及ぶ経営塾カリキュラムが始まった。私が入塾した第20期は過去最大規模の63名、日本全国から性別も年齢も業態もバラバラなメンバーが集まっていた。塾生の中には仕事上の繋がりから、既に既知の間柄のものもいたりして初日から意外と賑やかに挨拶が交わされていたように思う。
講義の一日のスケジュールは午前中に1コマ、午後に2コマを標準形式とし、1コマは1時間40分みっちり行われた。これが12月までの7ヵ月間で計26コマ組まれていた。講義内容は広範に網羅されておりここではとてもすべては紹介できないが、田中塾長の廃棄物処理事業概論に始まり、労働安全の注意点と労災事故防止への対処、リスクマネジメント論、産業廃棄物処理技術のあれこれ、廃棄物行政の現状と今後の展望、廃棄物業界における事業承継・相続やM&Aに関する講義、財務・金融分野に関しては財務諸表の読み方から事業改善への活用方法などなど。これら教科書的内容の講義に加え、講師の方の経営現場で実際の起きたこと、ご経験談などをお話いただく講義なども多々あった。塾生全員ひっきりなしに鳴る顧客からの電話や、メールへの対応等現業を抱えながらの講義出席で大変であったと思うが、講義への出席率はかなり高く、皆真剣に講師の話に耳を傾けていた。講義後には毎回聴講レポートを提出するが、これはその日の講義内容を頭の中で再整理し理解を定着させるには良かった。
私個人的には株式会社ミダックホールディングス加藤代表取締役社長の東証一部上場までの道のりのお話、株式会社JEMS鈴木常務取締役のAI・IoT活用の可能性のお話のほか、石坂産業株式会社石坂代表取締役の創業から現在に至るまでの様々な取組みに関するお話が非常に面白く興味深かった。実経験や現業からの生きた情報が多く、会社に戻ってすぐに周りに話したいと思うような、今後の自社経営のヒントが随所にちりばめられていた。
想定外だった合宿
入塾当初の私にとって最大の憂鬱は、夏と秋に予定されている2回の合宿だった。そもそも団体行動が苦手な私は、この年齢になってつい最近名刺交換したばかりの良く知らない63人と、たった2日間とはいえ合宿という集団生活(しかも夏と秋の2回)を送ることにかなりの抵抗感があった。また自分の業界知識の乏しさも合宿参加が憂鬱になる一因であった。皆の専門的な会話についていけるだろうかと。
ただ、私のこの思いは夏季合宿が終わるころには180度変わっていた。
最初の夏季合宿は開塾間もない7月に大阪で行われた。プログラムは、互いの会社のことを知るための会社紹介セッションと、事前に財団が設定した複数のテーマに関するワークショップ形式でのグループ討議と発表だった。
ワークショップでのディスカッションはチームワークが重要だ。決められた時間内で議論をし、結論をまとめ発表しなければならない。そのためにはグループ内の役割分担が非常に重要となるが私のグループはその点非常にハマりそれぞれが一番持ち味を発揮できる役割を担っていたと思う。議論開始直後こそお互い様子見の雰囲気だったが、そこは各社において責任あるポジションを任されている塾生だけあり徐々に活発な意見交換が始まった。業界知識の乏しい私にも皆優しく分かりやすく解説してくれたおかげで私もしっかり議論に参加でき、段々と楽しくなったことを覚えている。議論はホテルでの簡単な夕食を挟み夜遅くまで続いたが、2日目の発表に向け、ある程度目途が付いたところで皆そろって十三の街に飲みに出かけた。
この時間が格別だった。初日の半分をかけた議論のおかげで知らないうちにグループ内で連帯感が生まれていた。時間を共に過ごした相手のことを知ろうと皆互いに色々な質問をし、また自身についても語り始めた。皆の話を聞くにつけそれぞれに色々な過去・境遇があり、様々な考え方を持っていることが分かった。俯瞰的にみれば一括りにされる世界にいながら、遠すぎず近すぎずという、ほど良い距離感とでもいうべきか、こういう場だからこそ話せること、こういう場でしか話せないことがあった。他のグループも皆飲みに出ていたし、あるグループは部屋飲みまで全員が参加して深夜まで語り合っていたという。この日を境に第20期塾生たちの結束は急速に強まった気がする。
気づけば合宿参加前の私の憂鬱はどこかに消えていた。明日合宿が終わってしまうのか、とさえ思っていた。

あっという間の卒塾式
夏季合宿の2日目の各グループによる発表はどこもその独創性に優れており非常に面白かった。現業を踏まえた等身大の内容だったことも、より発表内容について理解を深めることができた一因であろう。この夏季合宿以降は、全体的に経営塾の雰囲気がガラリと変わったと感じた。8月からは通常の講義に戻ったが第20期として一体感が出てきたように思う。
10月の秋季合宿は中計策定と戦略立案の考え方やプロセスを学んだが、合宿前には膨大な量の事前課題を提出しなければならず、その提出には一苦労した。11月には城南島東京スーパーエコタウンのある複数の企業の施設見学にも行った。
気付けばあっという間に12月に入り、経営塾としての最後の講義は終了した。この最後の講義が終わった瞬間は何とも言えない非常に寂しい思いになったことを記憶している。このような思いを抱くとは入塾当初は想像すらしていなかった。
そして卒塾面談を経て1月末、第20期経営塾塾生は一人の脱落者も出すことなく、全員無事に卒塾した。

経営塾を振り返ってみて
終わってみれば本当にあっという間の6ヵ月だった。第20期の同期63人は色々な思いを持って偶然にも同じタイミングでこの経営塾に入塾した。そしてまた、それぞれの持ち場に戻っていった。
経営塾の塾生として過ごしたこの6ヵ月の間に生まれた繋がりを、経営塾の卒塾と共に終わらせてしまうのはあまりにももったいないと思うし、もしそうなってしまったら悲しいとも思う。先にも書いたが私は今まで孤独で人見知りだった。故に当初は経営塾の入塾にはとても消極的だった。知り合いもいないし講義内容は堅苦しそうだったし(実際難しい話も多かったが)、合宿なんて面倒だし6ヵ月なんてとても続かないだろうとも思っていた。それが卒塾した今、あっという間の6ヵ月だった、そしてこれからも皆と繋がっていたいと思うまでに至った。
経営塾というのは不思議な空間だ。商売敵となりうる競合他社の人間と机を並べて勉強し、講義後は時間の許す限り夜遅くまで飲みながら様々なことを語らい、合宿と称しては同じ釜の飯を食い夜まで喧々諤々と議論をする。
会社という枠を超え、年齢を超え、業態を超え、役職や肩書きを超え、この経営塾がなければおそらく一生交わることのなかったであろう人たち、全く異なるバックグラウンドを持った人たちと出会える不思議な場所、それが経営塾だ。ここで私は自分の枠を超えた新しい考え方・発想などに出会えた。一生の付き合いになるだろうと思える繋がりも得た。
私にとって経営塾は一言で言えば、孤独だった自分に新たな世界を見せてくれた、決して大げさではなく自分を変えてくれた空間だった。私は皆から与えられるばかりで、同じように返せていたのだろうかと思う。いや返せていないだろうな、これからまだまだ先は長いからじっくりと返していきたいと思う。
更なる発展のため、今後の経営塾に期待すること
私見ではあるが、私が経営塾に対し、その良き伝統を受け継いでほしいこと、変えることを検討しても良いのではと提言できることが合計で4つある。一塾生の独り言と思っていただきたい。
1つ目、当初はかなり厳しいと思っていた毎回の講義及び合宿への物理的な出席要請。この出席率が卒塾の条件になっており、また優秀終了証の判定基準にもなっていた。入塾前は講義のために毎回わざわざ東京まで行くのは面倒だな、と現業の忙しさを理由にややもすればリモートでの講義参加に心が傾きがちになるところ、この条件のおかげで多少の無理をして諸種調整し講義に参加したが、その労力と引き換えに次第に塾生間の交流は深まっていった。当初想定していなかったこの副産物こそが、お金を出しても得ることのない唯一無二の財産になった。近年はリモート会議の普及など多様な働き方に対応した便利なツールが出てきているが、可能な限り対面に拘るこのアナログな講義形式は残していってほしいと思う。そして合宿は続けていってほしいと思う。
2つ目、12月に実施する卒塾面談を講義の前後(特に講義後)に設定するのはなるべく避けた方が良い。面談が設定されている塾生はその時間まで拘束されることになり、塾生同士交流を深める限りある時間が削られてしまう。
3つ目、秋季合宿について。合宿の最大の魅力は塾生同士共に過ごす時間を長く確保できる点にある。この考えに則れば、合宿は各人による事前課題の披露や講師による一方通行的な講義ではなく、ワークショップで意見を交換しながら議論を尽くし、その中で理解を深め新たな気づきを得るための場とすべきだ。今回の秋季合宿の進め方であれば教室スタイルの講義でも良かった。テーマ設定は非常に興味深く重要でもあるだけに自分の中では少し不完全燃焼感が残った。
最後に、名称である「経営塾」について。私は結構カタチから入る人間だが、一言で言えばこの名称は、「古臭く堅苦しい」というイメージがある。2004年に始まったこの経営塾は、その事業開始当初こそ経営者層を主たる受講生として始まったと思うが、この第20期に至るまでにその主たる参加者の顔ぶれは次世代を担う若き人材へと変化してきている。また近年は自社の経営課題への取り組みのみならず、日本国内の動静脈産業連携の他、地球環境の将来に対する展望や責務など講義内容も広範に変化している。こういった無限に広がる未来世界の課題に対し、果敢に挑戦する有望な人材を集め、育てる場所という目線で名称を含むブランディングを再構築してはどうか。
最後に、
冒頭にも記述したとおり、私は極度の人見知りである。とにかくこの経営塾への参加は憂鬱以外の何モノでもなかった。もし今、私と同じように経営塾への参加を躊躇している方或いは憂鬱だなと感じている方がいらっしゃるのであれば、その方に私が申し上げられることは一つだけである。その先へ一歩、踏み出そう。そうすればその先には自分が想像しなかった世界が広がっているはずだ。財団へのお世辞ではなく、今の私が伝えたいことはこの一点に尽きる。
最後になるが、この経営塾を主催している財団関係者の皆様並びに講義を行ってくださった多くの先生方にはこの場をお借りして厚く御礼を申し上げる。63名もの塾生を纏め8か月の間滞りなくプログラムを完遂するためには並々ならぬご苦労があったと思う。改めて感謝申し上げたい。そしてまた第20期の同期のみなさま、これからもどうぞよろしく。