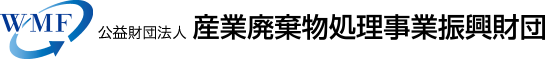島津製作所の自己循環型リサイクル(自社の梱包材プラをポリ容器に再生し自社で利用)へのパートナー協力
|
資源循環を促進するためには動静脈連携が欠かせないことから、本誌では、こうした取組の事例をご紹介しています。 今回は、株式会社ホームケルンが、精密機械製造大手の島津製作所の自己循環型リサイクル(自社の梱包材プラをポリ容器に再生し自社で利用)に協働・連携した取組をご紹介していただきます。 なお、本記事は、財団が同社を取材した内容を財団の責任で取りまとめたものです。ご多忙のなかご協力をいただき感謝申し上げます。 |
本取組みに至った経緯
 国本 武 社長
国本 武 社長
島津製作所とは二十年来のお取引をしています。今回のマテリアルリサイクルのお話は、約5年前に、島津製作所の環境マネージャーの方からご相談をいただきました。部品や医療機器等の梱包などに使うストレッチフィルムやエア緩衝材などの梱包材は、機器等の納入先から持ち帰ります。本社(三条工場)に集まった梱包材の処理は、以前は当社で受託してRPFとしてサーマルリカバリしていました。これについて島津製作所から、梱包材をポリエチレン容器(以下、ポリ容器)に再生して、社内で利用する自己循環リサイクル(クローズドループリサイクル)に取り組みたいので協力してほしい、とご相談を受けました。当社としても、お客様とともにマテリアルリサイクルに挑戦できることは大変ありがたく、ぜひともご一緒に取り組むことにしました。
島津製作所では、部品の梱包などに使うフィルム状の梱包材を大量に使っており、これを自社の事業に活用する方法を検討されていました。同社では各種分析の際に排出される廃液の保管にポリ容器を使っており、これまでバージンプラスチック製を購入していましたが、廃液はポリ容器ごと焼却しています。このようなシングルユースのポリ容器に対して、自社から発生した再生ペレットを活用する取組が「自己循環型リサイクル」です。
開発・評価までに5年の月日
梱包材とポリ容器のプラスチック材質等について
再生の原料となる、部品や医療機器等の荷崩れ防止用の梱包に使うストレッチフィルムやエア緩衝材の材質はポリエチレン(PE)で、一般にフィルムやシートなど柔らかいプラスチック製品の素材として広く使われています。一方、再生製品であるポリ容器は、同社では薬剤を廃棄する際の容量10リットルのタンクとして使用するもので、一定の強度や耐薬品性等が必要になります。ポリ容器の一般的な材質は高密度ポリエチレン(HDPE)に対し、ストレッチフィルム等の梱包材は低密度ポリエチレン(LDPE、LLDPE)であり、強度面等の検討が重要になります(表1参照)。
表1 代表的なポリエチレン(PE)の種類
|
LDPE |
高圧法低密度ポリエチレン(ラジカル重合) |
| LLDPE |
直鎖状低密度ポリエチレン(中低圧法,イオン重合) |
|
HDPE |
中低圧法高密度ポリエチレン(イオン重合)低圧法高密度ポリエチレン(イオン重合) |
(「化学と工業」Vol.69-7 July 2016より、事務局にて作成)
マテリアルリサイクルの品質確保のための役割分担等
プラスチックのマテリアルリサイクル(以下、再生)を行う場合、汚れや異物の付着があると品質上マイナスになります。異物については、梱包材に製品仕様を記載したシールが張られており、除去する必要がありました。これについては、可能な限り島津製作所において除去していただくことになりました。除去の方法は、シールの粘着力が強いために剥がすことは難しく、実際には引きちぎるような作業になります。ハサミやカッターナイフの使用は危険なため避けています。汚れについても、集まっている梱包材を島津製作所の担当の方が確認し、汚れが大きいものは対象外として引き続きRPFにしています。梱包材の屋外保管は少ないため比較的品質は良好で、島津製作所において排出の前に分別していただいていますが、当社に搬入された分別済の梱包材についても、より厳しく再度選別を行い、水滴や汚れ、小さなシールの除去を行っています。
また、梱包材は基本的に透明ですが、一部黒インクで文字が印刷されています。これにより、再生ペレットはバージン材のような真っ白なペレットにはならず、やや灰色に着色します。出来上がったポリ容器も、やや灰色になりますが、機能や物性上は問題がないため、そのままペレットにすることにしました(図1,2参照)。
 図1 左:ストレッチフィルム(LLDPE) 右:ポリ袋(LDPE)
図1 左:ストレッチフィルム(LLDPE) 右:ポリ袋(LDPE)
 図2 バージンペレットと再生ペレットの外観の比較
図2 バージンペレットと再生ペレットの外観の比較
再生工程の検討
梱包材から再生ペレットを製造する工程、バージンペレットと再生ペレットをブレンドして、ブロー成形でポリ容器を成形する工程について、どのように進めるか検討した結果、前者は当社において設備導入して実施し、後者は外部委託することとしました。
前者の工程では、受け入れた梱包材を再度選別したのち、破砕・乾燥、押出、異物除去、切断、水冷を行う、一体型でホットカットタイプのペレタイザーを選定しました。梱包材の品質が良く、施設設置にあたって地元調整の問題がないよう、洗浄工程のないフローです。環境省の補助金を受けて設備導入しました(図3参照)。
 図3 ペレット製造機 全景
図3 ペレット製造機 全景
造粒された再生ペレットは、ブロー成形を行っている成形会社に持ち込み、バージン材とブレンドしてブロー成形※します(図4参照)。
※ブロー成形(吹込み成形、中空成形)とは、加熱した樹脂を型に入れ、樹脂の内側から空気を吹き込むことで型の形状に成形する方法
 図4 成形機 全景
図4 成形機 全景
試作と評価
以上の方針のもと、2022年7月から試作と評価を繰り返し行いました。特に試行錯誤したのは、最適なブレンド比率とブレンド比率に応じた最適な金型形状の検討です。量産化を前提として
- 制作工程での無駄の排除(バリの減量)
- 使用に耐え得る強度
- 新品と同等の耐薬品性
を指標として検討を進めました。
具体的には、使用ペレット全量のうち、梱包材由来ペレットの含有率を50%、40%、30%と条件を振って検証しました。50%含有は指で軽く押すだけで凹み、容器上部はともかく、容器の下部が弱くなると廃液の漏出リスクが高くなるため、候補から除外しました。一方、30%含有は耐圧は使用に耐え得ると評価できましたが、角部分については樹脂の定着が悪く、厚さが薄くなることで少しの圧力で凹みが生じました。樹脂の定着性の悪さは、コーナーを削り、やや鈍角な形状にすることで対応し解決しました。
 図5 作業の様子と試作品
図5 作業の様子と試作品
続いて、形状変更後のポリ容器について、梱包材由来ペレットの含有率40%と30%の場合について検証しました。形状変更により樹脂の薄膜化は大幅に改善されましたが、量産化(1,000個)の検証により、含有率40%の場合は、若干の凹みの発生が約1割あり、口の部分の収縮により内ブタが閉まりにくい容器が数個発生しました。この結果、次回の製造ロット以降は、含有率30%とすることとしました。
耐薬品性については、2022年2月より実際の薬品(アセトニトリル、強酸、無機混合廃液等)を用いて1~1.5年保管し、いずれもピンホールや薄膜化等の異常は確認されず、シングルユースであることを前提に使用に耐え得るとの評価結果になりました。
現在は、量産化により、再生ポリ容器は、バージン由来の新品のポリ容器よりも若干安価に製造販売できており、病院の感染性廃棄物用ポリ容器(20リットル)にも利用を拡げて、廃液用ポリ容器を2,000個/年、感染性容器を600個/年のペースで製造販売しています。
 図6 最終完成品
図6 最終完成品
自己循環型リサイクルスキームの拡大にむけて
島津製作所では、本社(三条工場)で始めたこの自己循環型リサイクルを、全国の工場に拡大できないか検討しています。また、この自己循環型リサイクルスキームは、自社内にとどまらず、大学等地域のサーキュラー・エコノミーへの移行にも貢献するものと考えており、京都には企業や大学など研究機関が多く、実験室で廃液ポリ容器は不可欠のため、本スキームの地域への展開にも取組んでいます。
このような普及活動によって、2023年5月23日に、島津製作所と龍谷大学が循環型社会づくりへの貢献に向けた「包括連携協定」を締結し、本スキームに同大学が加わりました。同大学では、学内で発生した使用済み梱包材を原料として成形した再生ポリ容器を、理工学部及び農学部の実験機器として採用しています。また、包括連携協定に基づき、同社の関係部門が同大学の環境教育に協力するなどの連携が始まっています。島津製作所では、京都府補助事業で取り組んだこの成果を、「京都発の新たな取組」として全国に広げていきたいしています。
当社としても、企業や大学等で発生する梱包材を、廃液ポリ容器等に再生する取組は、多くの企業等に共通する課題に対する一つの解決策として取り組み易いのではないか、と考えており、ご関心ある方にはぜひご参加いただければと思います。どうぞよろしくお願いいたします。